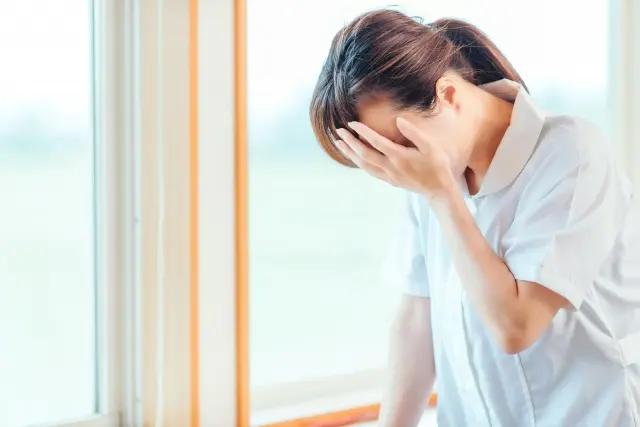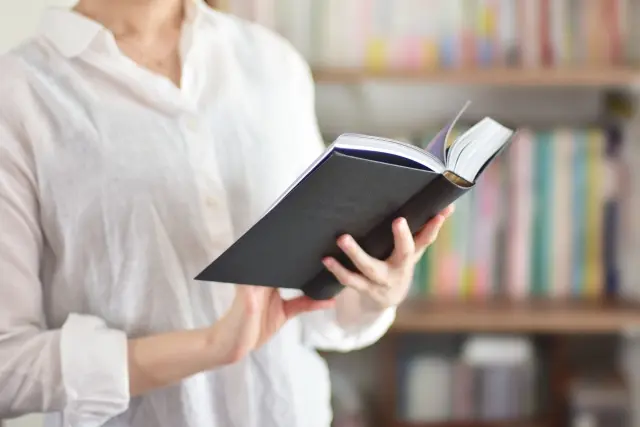看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説
.jpeg)
看護師が介護福祉の分野において「スキルアップしたい」「もっと頼りになる存在になりたい」と感じる場合、資格取得を目指すことが選択肢の1つです。
本記事では、介護・福祉に関連する資格の中でも、看護業務に直結する知識が深まるだけでなく、高齢化が進む現代において求められる対応力も身に付く資格を12個厳選し、詳しく解説します。
1. 看護師がプラスで資格を取得するメリット
介護福祉分野において活躍したい看護師がプラスで資格を取ることには、下記のメリットがあります。
1-1.キャリアパスが広がる
看護師がプラスで資格を取ることで、キャリアパスの選択肢が広がります。例えば、ケアマネジャー(介護支援専門員)や高齢者ケアストレスカウンセラーの資格を取得すれば、介護施設でのキャリアが開け、生活支援にも深く関わることができます。
また、認知症ケア専門士を取得した場合、病院内で認知症ケアに特化した専門職としても活動できるようになり、今後のキャリアの選択肢の幅が広がります。
1-2.知識力・スキルの向上
資格を取得するための学習において、看護師免許だけでは得ることができない専門的な知識を学ぶことができます。例えば、終末期ケア専門士を取得すれば、終末期の患者とその家族を支えるための深い理解と技術が身につきます。
また、認知症ライフパートナーや認知症介助士では、認知症に関する幅広い知識を習得できるため、質の高い認知症ケアが可能になるでしょう。
1-3.自信とやりがい
資格を取得することで自分の成長を実感できるとともに、患者に寄り添える看護師としての自信に繋がります。
認知症予防レクインストラクターや高齢者傾聴スペシャリスト、シニアピアカウンセラーの資格を取得することで、科学的根拠に基づいた質の高いケアが可能になります。
そうした適切なケアを通じて感謝の気持ちを述べられた際は、より一層のやりがいを感じられるでしょう。
1-4.収入アップ
資格取得により、収入アップが見込まれるのも大きなメリットです。介護予防運動指導員や認知症ケア専門士、終末期ケア専門士などの資格を持つことで、資格手当が支給される可能性があります。
資格手当や基本給アップなど、給与改定の規定は勤務先で異なるため、事前に確認しておきましょう。
1-5.転職活動でのアピールポイントになる
看護師にプラスして関連資格を有することで、転職活動においてもアピールポイントになります。
例えば、認知症ケア指導管理士や音楽健康指導士などの資格があれば、介護施設や行政機関、地域支援団体など、転職先の選択肢が広がり、好条件の求人に応募しやすくなります。
さらに、配置基準で求められる資格を複数所持していると、より重宝されるでしょう。
2. 看護師のスキルアップに繋がる+αの資格4選
介護福祉の現場で行うレクレーションや実践スキルに関する資格を取得することで、高齢者の心身やライフステージの変化に合わせて対応することができ看護師としてのスキルアップに繋がります。
この章では、看護師のスキルアップに繋がる介護福祉に関する資格を紹介します。
2-1.レクリエーション介護士1級
レクリエーション介護士1級は、レクリエーション介護士2級取得者が受講することができ、利用者の要介護度や家族が抱える課題に対して、短期・長期的な視点でレクリエーションを計画・実施し、高齢者一人一人の状況にあわせたアレンジをすることが可能となります。
さらに、レクリエーションの意義を深く理解し、その重要性を他のスタッフや家族に伝えることができるようになります。
取得にあたっては、4日間の通学講座で「レクリエーションの意義」や「アレンジ方法」「自立支援計画」などを学び、実技試験では10分間の実演を行います。筆記試験では、所要時間2時間のうちに選択および記述問題(64~66問)と小論文(500文字程度)が出題されます。さらに、資格取得後には、3施設での現場実習も必要です。
資格取得にかかる時間は、講座受講に4日間、実技試験、筆記試験、実習を含めて、約1〜2ヶ月が目安です。費用は91,300円で、テキスト代や試験料が含まれています。
出典:日本アクティブコミュニティ協会「レクリエーション介護士1級ガイド」
2-2.認知症予防レクインストラクター®
認知症予防レクインストラクターは、認知症の発症予防や進行遅延を目的としたレクリエーションの提供に特化した資格です。認知症に関する基本的な知識や高齢者の心身の変化に対する理解をもとに、軽度から中等度の認知症を持つ方々に対する適切なレクリエーションの提供が可能です。
資格取得には、指定の認定教育機関でカリキュラムを履修し、JADP認定の介護レクインストラクター®を取得後、試験に合格する必要があります。試験は在宅受験が可能で、協会のウェブサイトから申し込むと試験問題が郵送され、得点率70%以上で合格となります。結果は答案受付後約1ヶ月で通知されます。受験料は5,600円です。
出典:日本能力開発推進協会 (JADP)「認知症予防レクインストラクター」
2-3.音楽健康指導士
音楽健康指導士は、音楽の力を活用して心身の健康を維持・向上させるスキルを習得できる資格です。
音楽レクリエーションを通じて、社会福祉施設や介護予防事業、民間フィールドなどで幅広く活躍できます。2級と準2級に分かれており、それぞれ学習内容や受講期間などが異なります。
| 資格名 | 特徴 | 受講形態 | 受講期間 | 費用 | 試験 |
| 準2級 | 音楽レクリエーションの基礎知識を習得し、教材を参考にしたセッションを実施可能 | ユーキャン通信講座による在宅学習 | 標準3ヶ月(最長6ヶ月) | 34,000円 | 在宅試験形式 |
| 2級 | オリジナルプログラムを作成し、目的に応じたセッションを計画・指導する能力を習得できる | 集合講座(準2級取得済みは2日間、未取得は3日間) | 教材到着から最大12ヶ月 | ・準2級取得者:69,400円 ・準2級未取得者:103,400円 | 集合講座後に実技試験(準2級取得者は免除) |
2-4.終末期ケア専門士
終末期ケア専門士は、患者や利用者の最期を支える専門知識と実践スキルを備えた資格です。医療・介護現場での多職種連携を見据え、終末期に特化したケアを提供できることを目指します。
看護師だけでなく、医師、薬剤師、歯科衛生士など医療に関連する職種が対象となり、2年以上の実務経験が受験資格として求められます。
公式テキストやWEB講習会を活用した自主学習が主で、試験では公式テキストと時事問題に基づいた内容が出題されます。試験の方法は、会場でパソコン試験(CBT試験)が行われます。
資格取得にかかる費用は、受験料として11,000円です。
3. 高齢者の生活を支える資格4選
介護施設や訪問介護など、さまざまな場で役立つ資格もあります。介護福祉の現場で高齢者の生活を支える資格を紹介します。
3-1.ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に基づく専門職で、要介護者や要支援者とその家族が適切な介護サービスを受けられるよう支援を行います。
利用者の希望や心身の状況を考慮し、在宅や施設で必要なサービスが受けられるようにケアプランを作成したり、市区町村やサービス事業者などと連絡調整を担ったりします。
受験資格は保健、福祉、医療分野で原則として5年間以上かつ900日以上の実務経験を有することです。受験手数料に関しては、各都道府県で異なるので確認する必要があります。
出典:厚生労働省「介護支援専門員/ケアマネジャー」
出典:社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員(試験問題作成)」
3-2.介護予防運動指導員
介護予防運動指導員は、高齢者の運動能力向上を目的に、安全かつ効果的な運動プログラムを提供し、高齢者の自立支援や生活の質の向上を支える専門資格です。
看護師や歯科衛生士、介護支援専門員といった医療・福祉の専門職の保持者や指定の研修修了者で実務経験が2年以上の者などが対象となっています。また、資格取得を目指して養成校で学ぶ学生も受講可能です。
受講料やテキスト代、修了証発行料については、講習会を実施する指定事業者によって異なりますが、9万円前後が目安とされています。
出典:東京都健康長寿医療センター研究所「介護予防運動指導員養成事業について」
3-3.高齢者ケアストレスカウンセラー
高齢者ケアストレスカウンセラーは、現代社会で増加するメンタル疾患への対応を目的に、基礎知識とスキルを身につけるための資格です。メンタル疾患の予防や精神的に不調をきたしている人々へのケアを行い、心の健康を支える役割を果たします。
試験は公式テキストおよび一般常識に基づいた内容から出題され、試験時間は60分、合格基準は正答率70%以上です。受験資格は18歳以上かつケアストレスカウンセラー資格を取得していることです。ただし、ケアストレスカウンセラー資格との併願受験ができます。
受験費用は12,000円で、合格後に認定登録を希望する場合は別途5,000円が必要です。
出典:職業技能振興会「ケアストレスカウンセラー(青少年・高齢者・企業中間管理職)」
3-4.シニアピアカウンセラー(高齢者傾聴スペシャリスト)
シニアピアカウンセラーは、施設や自宅などで生活する高齢者の元に赴き、日常での悩みや相談を聴くことで、心的ケアを行うための資格です。
「受容」「傾聴」「共感」の3つの基本スキルによるカウンセリング技術を学び、高齢者の気持ちに寄り添う声掛けを行えるようになります。また、このカウンセリング技法により、信頼関係を築き、安心感を与えることにつながります。
似たような資格に高齢者傾聴スペシャリストやJADP認定シニアピアカウンセラー® もあります。
講座修了後は、講座で使用したテキストを見ながらの在宅受験が認められています。試験内容は傾聴の理論や基本技術、実践的な知識が中心で、70%以上の得点率で合格できます。
受講費用は68,800円(税込)、受験料は5,600円(税込)です。
4. 認知症ケアのスキルアップ資格4選
認知症ケアには、基礎的な介護スキルに加えて、認知症における知識と深い理解が必要です。認知症ケアのスキルアップに繋がる資格を紹介します。
4-1.認知症ケア指導管理士
認知症ケア指導管理士は、認知症の方への理解を深め、適切な支援を行うための専門知識と実践的スキルを身につける資格です。認知症患者の生活の質向上に寄与することを目的としており、初級・上級の2段階に分かれています。
初級資格は、高校生以上であれば誰でも受験できます。試験問題は公式テキストから出題され、合格基準は総得点の70%以上です(難易度に応じた補正あり)。受験料は一般7,500円、学生は4,000円です。
初級資格を取得した後は、上級資格を目指すことも可能です。上級資格は、認知症ケアの高度な専門知識を身につけ、他のスタッフへの指導・育成を行う指導者としてのスキルを培うことを目的としています。資格取得後は、医療や福祉の現場でのキャリアアップが期待されます。
一次試験合格者のみが二次試験を受験できます。試験費用は一次試験が12,000円、二次試験が6,000円です。
出典:職業技能振興会「認知症ケア指導管理士(初級)認定試験」
出典:職業技能振興会「上級認知症ケア指導管理士認定試験」
4-2.認知症ケア専門士
認知症ケア専門士は、認知症に関する高度な知識と技能を有し、介護や医療の現場で認知症ケアを実践する専門人材を育成する資格です。認知症ケア専門士の試験は、認知症ケアの実務経験を3年以上有する者が受験できます。
【1次試験】
「認知症ケアの基礎」「認知症ケアの実際Ⅰ:総論」「認知症ケアの実際Ⅱ:各論」「認知症ケアにおける社会資源」の4分野に分かれており、合格基準は各分野で70%以上です。
試験費用は1分野あたり3,000円、全4分野を受験する場合は合計12,000円となります。合格できた分野は5年間合格が認められるため、次試験では残りの分野のみ受験することができます。
【2次試験】
事例を基にした3つの論述問題が出題されます。
ここでは、認知症ケアの具体的な状況に対する判断力や、実際にどのようにケアを提供するかを文章で表現する能力が求められます。試験費用は8,000円です。
また、認知症ケア専門士を取得後、「専門士としての経験が3年以上」「認知症ケア上級専門士研修会を修了していること」などの要件をクリアすると、上級認定ケア専門士への受験資格を得ることができます。
上級認知症ケア専門士は、指導者としての責務を担い、チームリーダーや教育担当者としてケア従事者を育成し、職場全体のケアの質を向上させることを目的としています。上級認知症ケア専門士の受験料は10,000円です。
出典:日本認知症ケア学会「認知症ケア専門士認定試験」
出典:認知症ケア専門士公式サイト「認知症ケア上級専門士」
4-3.認知症ライフパートナー
認知症ライフパートナーは、認知症の方々がその人らしく日常生活を送れるよう支援する専門職です。認知症の方の過去の生活経験や価値観を尊重しながら、適切なケアを提供します。
日常生活におけるコミュニケーションが難しい場面でも、傾聴技術や回想法を駆使し、音楽や園芸などのアクティビティを活用することで、本人の楽しみや生きがいを引き出します。
認知症ライフパートナーには1級・2級・3級があります。
【3級検定試験】
学歴や年齢、国籍を問わず誰でも受験可能で、受験料は6,500円です。合格基準は100点満点中70点以上です。
【2級検定試験】
受験資格に制限がありません。受験料は10,500円で、3級より一歩進んだ知識とスキルが求められます。この試験も100点満点中70点以上が合格基準です。
【1級検定試験】
2級合格者のみが受験できます。受験料は15,000円です。出題内容は公式テキストに準拠しますが、一部テキスト外の問題も含まれるため、幅広い知識と実践的な能力が必要です。
出典:日本認知症コミュニケーション協議会「検定試験:検定概要」
4-4.認知症介助士
認知症介助士は、認知症についての基本的な知識と適切な対応方法を学び、家庭や職場、地域社会において認知症の方を支援するスキルを身につける資格です。
認知症の症状や行動の特徴を理解し、コミュニケーション技術を活用して認知症の方に寄り添いながら支援を行うことを目的としています。
認知症介助士の試験は、受験資格に制限がなく、学歴、年齢、性別、国籍を問わず、誰でも受験可能です。自身のスケジュールや学習スタイルに合わせて、4つの方法から受験方法を選ぶことができます。
| 受験方法 | 概要 | 受験料 |
| 認知症介助セミナー(検定試験付き) | セミナー受講後に検定試験も同日に受験可能 | テキスト込み:19,800円 テキスト持参:16,500円 |
| 共育センターでの検定試験 | 東京や大阪の共育センターで指定された日時に集合して受験 | 3,300円 |
| 全国のCBTセンターでの検定試験 | 全国のCBT試験会場でパソコンを使用して選択式試験を受験 | 3,300円 |
| インターネット経由でのIBT試験 | インターネット環境があれば自宅など好きな場所で受験 | 3,300円 |
5. まとめ
看護師が介護福祉関連の民間資格を取得することには、キャリアパスが広がる、知識力・スキルの向上、収入アップ、転職活動でのアピールポイントになるなど、さまざまなメリットがあります。今回ご紹介した12の資格は、高齢化が進む現代において、より専門的で効果的なケアを提供するために役立つものばかりです。
それぞれ受験方法や学習スタイルが異なるため、ライフスタイルや目的に合わせて選択してください。看護師としての可能性を広げるため、ぜひこれらの資格取得を検討してみてください。
relation
関連記事-
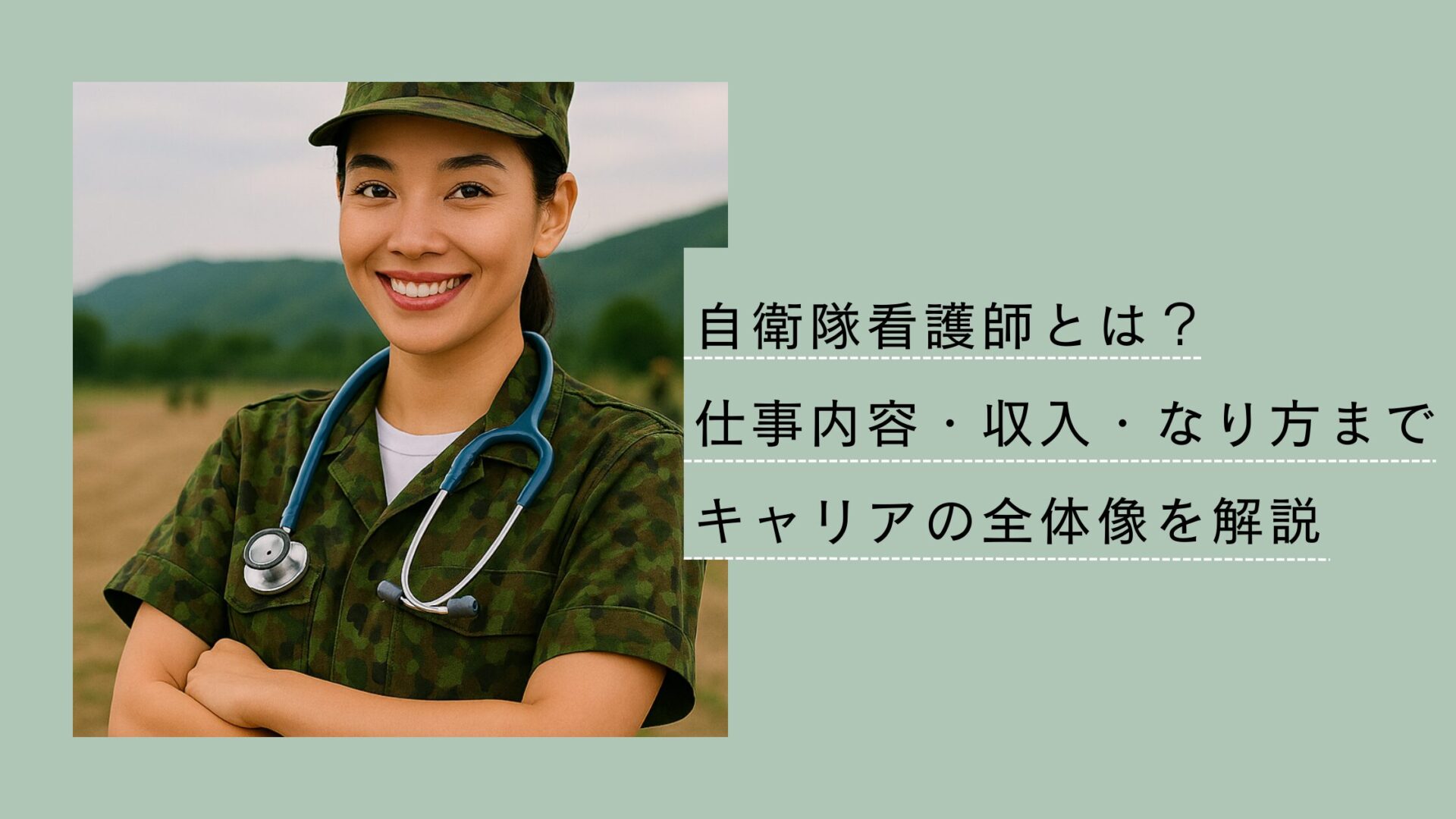
自衛隊看護師という働き方|仕事内容・収入・キャリアの始め方を詳しく解説
-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説
-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説
-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント
-
.jpeg)
皮膚科看護師になる前に知りたい全知識|仕事内容・職場・年収・向いている人
-
-1.jpeg)
看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント
-
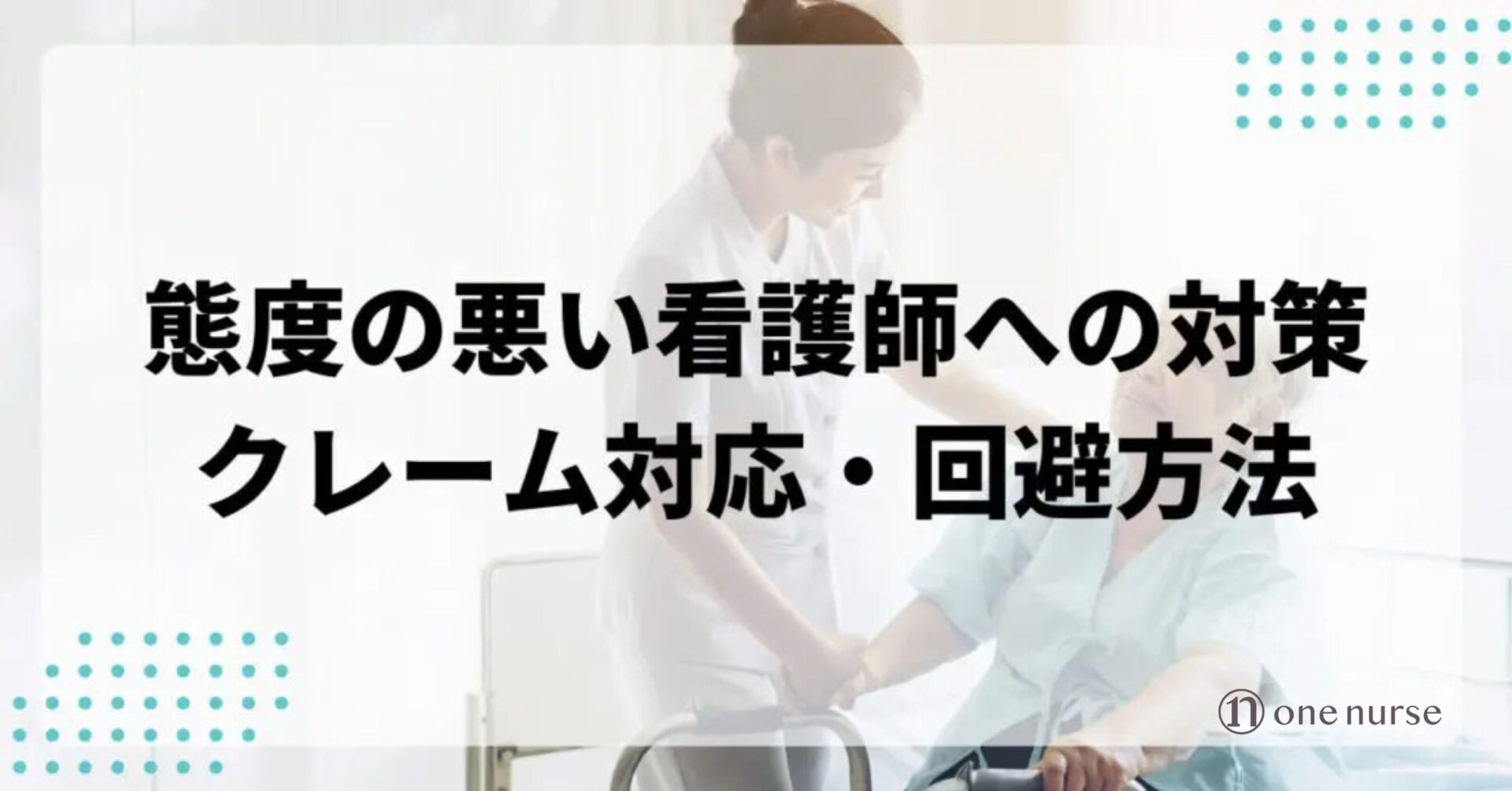
態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説
-

メイクセラピー(化粧療法)の効果とは?メイクセラピストとして働く方法も解説
-
.jpeg)
災害看護専門看護師とは?仕事内容や役割からなり方まで解説
-

フライトナースになるには?必要な資格・経験から実際の仕事内容まで
-
.jpeg)
エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説
-
.jpeg)
【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?
-
.jpeg)
看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選
-
.jpeg)
看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説
-
.jpeg)
「眼科看護師」とは?視能訓練士との違いや仕事内容から年収まで解説
-
.jpeg)
看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説
-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣
-
.jpeg)
空港看護師(エアポートナース)2種を紹介|検疫官と空港クリニックの仕事や給料を徹...
-
.jpeg)
看護師もダブルライセンスで働く時代!?おすすめ資格14選
-

今、医療現場で「特定看護師」が活躍している?行えること・なる方法を解説
-
.jpeg)
スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介
-

【希少なお仕事】クルーズ船の看護師「シップナース」 船上の仕事内容や働き方とは?
-

山岳看護師ってどんな仕事?山岳看護師になるための資格と仕事内容について
-

美容クリニックの看護師として働きたい方必見|仕事内容や給与などを徹底解説
-

精神科の看護師の仕事とは?一般診療科との違いややりがいを紹介
-

企業で働く看護師・ナースエデュケーターとは?病院勤務とは違った魅力を解説
-

看護師にとって楽な仕事とは?転職時におすすめの科と施設を紹介
-

治験コーディネーター(CRC)として働く看護師の仕事内容|口コミも紹介
-

看護師の専門性を活かす「アレルギーエデュケーター」になるには?注目が集まる理由と...
-

小児科看護師の仕事内容は?1日のスケジュールややりがいを解説
-

【2025年最新】男性看護師の割合・年収・就職先は?うまく働く方法も解説
-
.jpeg)
ナースプラクティショナー(診療看護師)ってどんな仕事?看護師との違いも解説
-

外科看護師とは?外科の魅力や悩み・求人のチェックポイントなど気になることを全部解...
-

緩和ケアとは?緩和ケア認定看護師の仕事内容やなる方法についても解説
-
.jpeg)
資格10種を紹介!がん看護の現状と将来性は?今求められる専門性と関連資格
-

看護師向け転職サイトのおすすめ15選!電話なしや求人の検索機能、職種などを紹介
-

コールセンターで働く看護師の仕事とは?仕事内容から勤務経験者の声まで解説
-

ツアーナースとは?病棟看護師との違いや特徴的な仕事内容・活かせる経験まで紹介
-
.jpeg)
看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選
-

災害支援ナースが果たす役割とは?新制度やDMATとの違い、なり方などを徹底解説
-
.jpeg)
介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る
-
.jpeg)
看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説
-
.jpeg)
腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説
-

愛玩動物看護師になるには?資格の特徴から試験情報まで徹底解説
-
.jpeg)
ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現
-
.jpeg)
新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント
-
.jpeg)
命の誕生に触れる「助産師」とは?仕事内容やなる方法・学費・支援制度まで解説
-
.jpeg)
透析看護師のやりがいとは?仕事内容と勤務スケジュールも併せて解説
-

健診・検診センターで働く看護師とは?働き方や仕事内容について解説
-

国際看護師として世界で活躍する魅力と夢を叶える具体的な方法を紹介
-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説
-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!
-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説
-

看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル
-

オペ室看護師(手術室看護師)とは?仕事内容・給与・勤務例・なり方などを解説
-

保健師とは?職場による仕事内容の違いや給与・キャリアパスなど徹底解説
-

潜在看護師とは?復職するための準備やおすすめの働き方・職場を解説
-

専門看護師とは?役割や認定看護師との違い、資格取得の条件や費用まで解説!
-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説
-

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響
-
.jpeg)
【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?
-

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説
-

看護師と保健師の違いとは?保健師の資格や仕事内容・年収を解説
-
.jpeg)
看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説
-
-1.jpeg)
看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント
-
.jpeg)
看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介
-
.jpeg)
エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説
-
.jpeg)
【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?
-
.jpeg)
看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント
-
.jpeg)
看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説
-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣
-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説
-
.jpeg)
スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介
-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説
-

看護師が産休や育休を取得するには?知っておきたい制度や手当について解説
-

看護師の身だしなみはなぜ大切?部位別のポイントやチェックリストを紹介
-
.jpeg)
看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説
-

【注射の苦手を克服】皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈注射のコツやテクニックを紹...
-
.jpeg)
看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説
-
.jpeg)
夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...
-
.jpeg)
ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現
-
.jpeg)
新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント
-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!
-

看護師のナース服に求められる条件は?モチベーションとの関連性についても解説
-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説
-

看護師を目指す際に利用できる奨学金・助成金・給付制度とは?条件や内容を解説
-
.jpeg)
【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?
-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~
Nurse Life, Your Way.
Nurse Life, Your Way.
Nurse Life, Your Way.
Nurse Life, Your Way.